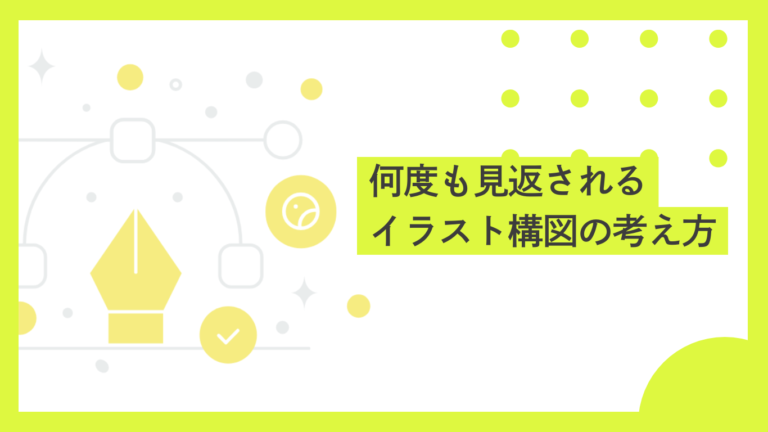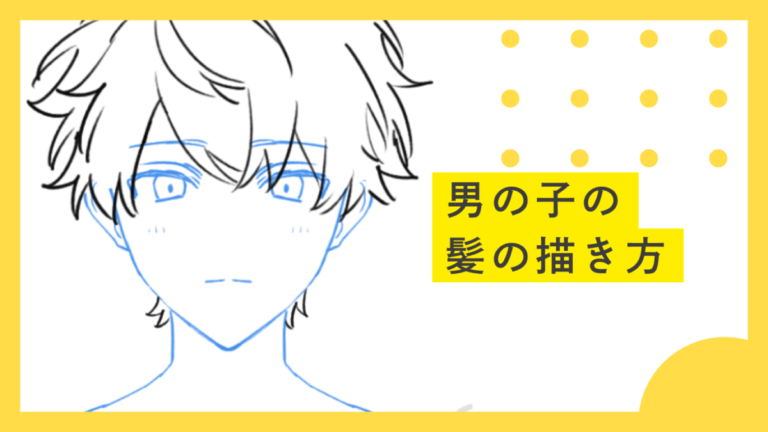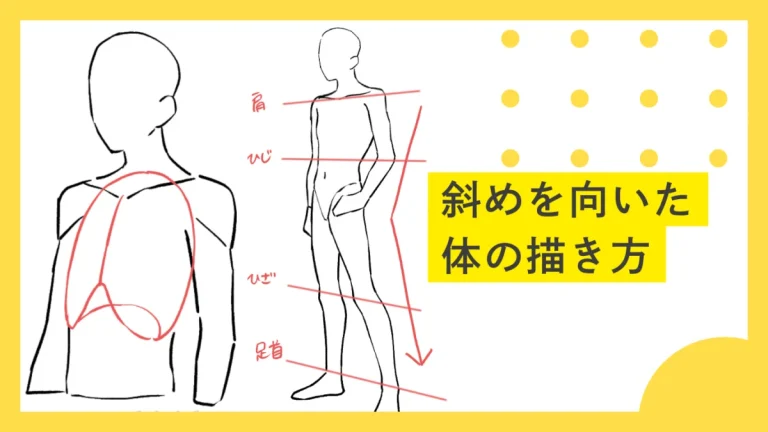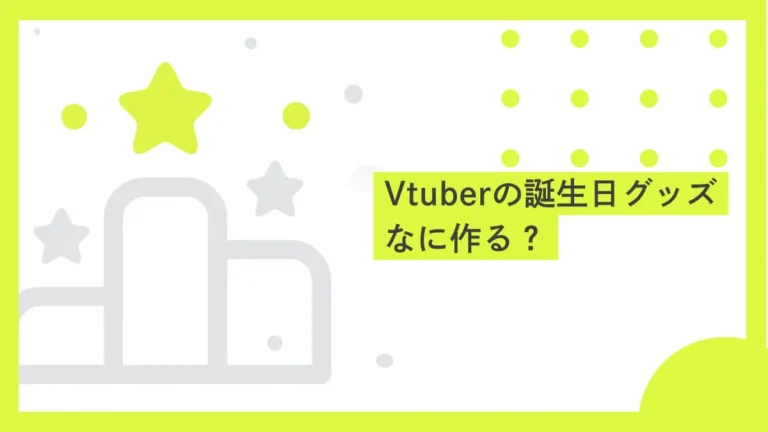数年前にこの「大・中・小の見どころを作る構図」という考え方を知り、それ以来、しっかりと一から構図を作るときには必ず意識するようになりました。
実際に取り入れてみると、作品に奥行きや視線の流れが生まれ、何度も見返したくなるようなイラストになると感じています。
ここでは、その考え方に自分なりの解釈やアレンジを加えながら解説します。
その構図の考え方とは、「モチーフを大・中・小の三段階に分けて配置する」というものです。
これを意識するだけで、作品に奥行きと視線の流れが生まれ、見る人を引き込む構図になります。
大モチーフ … 画面を支配する形。最も視線を集めたい主役や背景の主要要素。
中モチーフ … 主役を引き立てる補助的な形。場面説明や物語の補足を担う要素。
小モチーフ … 細部の装飾や遊び心の形。鑑賞者の再発見や物語の深掘りにつながる。
大モチーフ:一目でテーマと状況を伝える主役
イラストにおける大モチーフは、画面の中で最も大きく描かれ、テーマや状況を一瞬で伝える役割を持ちます。
観る人の視線はまずここに向かい、その印象が絵全体の第一印象を決定します。
例えば、女の子が川辺でアヒルに餌をあげている場面なら、大モチーフは女の子そのものです。
餌をあげる手の位置や姿勢、視線の方向など、行動がはっきりわかる形に描くことで、見る人は一目で「何が起きているのか」を理解できます。
大モチーフはただ大きければ良いわけではありません。背景とのコントラストや色の差をつけ、形の輪郭を明瞭にすることで、さらに視線を引き寄せます。
また、他の要素と干渉しすぎないように余白を持たせることで、主役としての存在感がより際立ちます。
大モチーフの考え方のポイント
- 画面内で最大サイズに設定する
- 主役の行動やポーズを明確にする
- 輪郭や形を背景からしっかり分離させる
- 明暗差や色の差で目を引く
- 周囲に余白を確保し、他モチーフとの干渉を防ぐ
一目でテーマと状況を伝える主役モチーフパターン集
1. 主役キャラクター+主要行動
例:女の子+アヒルに餌をあげる
意図:行動そのものがテーマを説明し、背景説明を不要にする
例:宇宙飛行士+無重力で本を読む
意図:キャラの職業や世界観を即理解させる
2. 主役キャラクター+象徴的アイテム
-
例:少年+巨大なカブトムシ
意図:関係性や物語の方向性をひと目で提示 -
例:魔法使い+杖から光が溢れる
意図:キャラの能力や役割を瞬時に伝える
3. 主役キャラクター+舞台の象徴
-
例:浴衣の女の子+夜空に花火
意図:舞台と季節感を一瞬で印象づける -
例:潜水服のキャラ+海底の遺跡
意図:場所とジャンル(冒険/探索)を即理解させる
4. 主役キャラクターのみ(背景最小限)
-
例:正面から見た戦士のポートレート
意図:人物の存在感や個性を前面に出し、背景に依存せずテーマを成立させる -
例:表情や服装のみでシーンを推測させる構図
意図:見る人の想像力を引き出す
5. 主役以外の存在を対比として使う
-
例:小さな女の子と巨大なアヒル
意図:サイズ差や関係性で印象を強くする -
例:勇敢な騎士と膝にしがみつく子供
意図:感情や状況を対比で即座に理解させる
中モチーフ:何度も見てもらえる仕掛け作り
中モチーフは、大モチーフの次に目に入る要素で、絵に物語や状況の深みを与えます。
観る人はまず主役に注目しますが、その後に中モチーフを見つけることで「この場面にはこんな背景があったのか」と気づき、鑑賞時間が延びます。
こうした再発見の積み重ねは、絵を何度も見返したくなる理由にもなります。
例えば、女の子がアヒルに餌をあげている場面で、足元に空の袋が転がっていれば「ずっと餌をあげていたんだ」と想像できます。
また、他のアヒルが餌に夢中な中、1羽だけ水浴びしているなど、小さなズレや変化を加えることで、場面が生き生きと感じられます。
中モチーフの考え方のポイント
-
時間や状況を示す痕跡を入れる
-
例:足元に空の餌袋
→ 「この子はずっと餌をあげ続けていたんだ」と、行動の前後関係を想像させる。場面に“時間の流れ”が加わる。 -
例:散らかった机
→ 「さっきまで作業していたのかも」と直前の行動を連想させ、背景の物語性を強化する。
-
-
登場人物や動物の関係性を表す配置や視線
-
例:アヒルの中に1羽だけ女の子を避けている
→ 主役との距離や心理的な関係を示す。観る人に「なぜ避けてるの?」という疑問を抱かせる。 -
例:友達同士で視線を交わしている
→ セリフがなくても交流や感情のやり取りを伝えられる。
-
-
全体の中に1つだけ違う行動や表情を混ぜる
-
例:1羽だけ水浴びしていて餌に興味なし
→ 集団の中での“例外”は視線を引き、場面の自然さとリアリティを高める。 -
例:全員が前を見ている中で1人だけ後ろを見ている
→ 「何を見ているんだろう?」と観る人の想像を促す。
-
-
想像を広げる小物を配置する
-
例:パン袋にハートマーク
→ 誰が用意したのか、そこに感情や人間関係が隠れているかもしれないと想像できる。 -
例:リュックからぬいぐるみが顔を出している
→ キャラクターの性格や趣味をさりげなく伝えられる。
-
このように、中モチーフは単なる“飾り”ではなく、「何を想像させたいか」という意図を持って選ぶことで、構図全体の完成度が大きく変わります。
何度も見てもらえる仕掛けパターン集
1. 時間や状況の痕跡
-
例:足元に空の餌袋 → 長く餌をあげていた
意図:背景に「時間の経過」を匂わせてストーリーを補完 -
例:散らかった机 → 直前まで作業していた
意図:シーン直前の出来事を想像させる
2. 登場人物の関係性
-
例:アヒルの中に1羽だけ女の子を避けている
意図:感情や性格の違いを演出してキャラを立たせる -
例:友達同士で目線を交わしている
意図:無言の交流を描き、物語性を増す
3. 小さな変化・ズレ
-
例:1羽だけ水浴びしていて餌に興味なし
意図:観察する楽しみを作り、視線を画面全体に回遊させる -
例:全員が前を見ている中、1人だけ後ろを見ている
意図:違和感で視線を引き、会話のきっかけを作る
4. 想像を誘う小物
-
例:パン袋にハートマーク → 誰かが用意した?
意図:背景設定や登場人物の関係性を想像させる -
例:リュックからぬいぐるみが顔を出している
意図:キャラクターの趣味や性格をさりげなく示す
小モチーフ:よく見た人だけが気づく遊び心
小モチーフは、作品に「発見する楽しみ」を加えるための隠れた仕掛けです。
最初の鑑賞では気づかないことが多く、二度目・三度目に見たときに「え、なにこれ!」という驚きや笑いが生まれます。
こうした要素は、作品への愛着やファン心理を強め、SNSで共有されやすくする効果もあります。
小モチーフは主役や中モチーフの邪魔にならないように、背景や小物の中にさりげなく仕込むのがポイントです。
時にはキャラクターやストーリーに関連するネタやパロディを入れて、知っている人だけが楽しめる“内輪のご褒美”にしても面白いでしょう。
小モチーフの考え方のポイント
-
背景や小物にさりげないモチーフを仕込む
-
例:草むらからカエルが顔を出している
→ 自然の中での出来事にリアリティと遊び心を加え、見つけた人にちょっとした達成感を与える。 -
例:アヒルの羽に1本だけ色違いがある
→ 小さな変化が“探し物”感覚を生み、何度も絵を見返したくなる。
-
-
ファンが喜ぶパロディや隠し要素を配置
-
例:パンの袋に「ご自由にお取りください」と書かれ、アヒルが袋を持っている
→ コミカルさと物語性を同時に演出し、SNSで話題になりやすい。 -
例:背景のポスターに「失われた靴下探してます」というネタ広告
→ 世界観を広げるユーモアで、作品の“住んでいる感”を強化。
-
-
食べ物や持ち物に意外性を混ぜる
-
例:女の子が普通のパンではなくたい焼きやドーナツをあげている
→ 予想外の組み合わせで笑いやツッコミを誘い、印象に残るシーンにする。 -
例:1羽のアヒルがアイスキャンディーをくわえている
→ 意味はないけれど「なぜ?」と想像を促し、ファン同士の会話のきっかけになる。
-
小モチーフは、あくまで“見つけた人だけが嬉しい要素”であることが重要です。
多すぎると主役の印象がぼやけるため、作品1枚につき1〜3カ所程度に絞り、見つけたときのインパクトを保ちましょう。
遊び心・ご褒美要素パターン集
1. 予想外なアイテム
-
主役があげている食べ物が、シーンと不釣り合い
-
例:アヒルにたい焼き、ドーナツ、ラーメン
-
-
動物やキャラが、明らかに似合わないものを持っている
-
例:アヒルがサングラス&金のネックレス
-
2. 背景に潜む隠しキャラ
-
草むらや木の陰から、別の動物やキャラクターが覗いている
-
過去の作品に登場したキャラがカメオ出演している
-
フレームの端にしか見えない「影」や「手」
3. 文字ネタ・看板ネタ
-
看板や張り紙の文字がギャグやパロディになっている
-
例:「アヒル専用駐車場」「持ち込みパン禁止」
-
-
食べ物屋のメニューに妙なものが混ざっている
-
例:「アヒルラーメン」「水草ケーキ」
-
4. 小物の違和感
-
服や持ち物に意味深な模様やロゴ
-
キャラの靴下の片方だけ柄が違う
-
リュックから場違いなものが飛び出している
-
例:パンではなく花束やぬいぐるみ
-
5. 行動のズレ
-
周りと全く違う動きをしているキャラ
-
例:餌をあげられているのに爆睡しているアヒル
-
-
何かに夢中になっているせいでメインの出来事に気づいてないキャラ
6. 隠しメッセージ
-
模様や装飾の中に、文字や絵をさりげなく隠す
-
雲や木の形がハートや動物になっている
7. シリーズ的遊び
-
前回の絵に出た小ネタが再登場(ファン向けの継続ネタ)
-
季節ごとに変わる隠しモチーフ
大・中・小のモチーフで作る構図の具体例一覧
以下の表では、具体的な構図例と、それぞれの大・中・小に当たる要素をまとめました。考え方の補足として参考になれば幸いです。
| 構図例 | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|
| 女の子が川辺でアヒルに餌をあげる | 女の子+アヒル(餌やりの行動でテーマを直感的に伝える) | 足元の空袋、1羽だけ別方向を向くアヒル(時間経過と個性を表現) | 草むらから覗くカエル、パンがたい焼き型(遊び心の発見) |
| 浴衣の女の子が夜空を見上げる | 浴衣の女の子+花火(舞台と季節感を一目で伝える) | 手に屋台の金魚すくい袋、友達らしき影(直前の行動と人間関係) | 屋台の値札に『謎の串焼き100円』、花火にハート型(隠しネタ) |
| 魔法使いが杖から光を放つ | 魔法使い+発光する杖(能力と役割を瞬時に提示) | 背景に戦いを見守る仲間、足元の魔法陣(状況と仲間の存在) | 魔法陣の模様に小動物、光の粒に星座の形(細部の遊び心) |
| 宇宙飛行士が無重力で本を読む | 宇宙飛行士+漂う本(世界観と日常の対比) | 窓の外に地球、背景に浮かぶカップやペン(生活感と舞台の補足) | 本のタイトルがジョーク、背景に小さなUFO(発見のご褒美) |
| 少年と巨大なカブトムシ | 少年+巨大なカブトムシ(関係性とテーマを強く印象づける) | 足元に虫取り網、背景の森の奥に光(物語の前後を示唆) | カブトムシの角に小鳥、少年の帽子に小さな虫(微笑ましい発見) |
- 大で「見たい」と思わせる
- 中で「もっと知りたい」と引き込む
- 小で「また見たい」と記憶に残す
この流れを意識して構図を作ると、1枚の絵から何度も楽しめる作品に仕上がります。